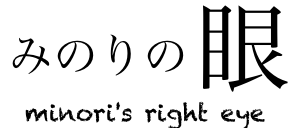加藤訓子ソロリサイタルシリーズ in サルビアホール vol.2 レポート
おかげさまで「加藤訓子「B A C H」J.S. Bach series vol. 1」 無事に終了しました。
ご来場いただいたお客さま、そして応援いただきました皆さま、本当にありがとうございました!
最高の響きを誇るサルビアホールに広がる加藤訓子さんの演奏は、そのポテンシャルを最大限引き出すものだったと思います。
おいでいただきましまお客さまの生の声を、許可をいただき、ここに転載します。ぜひご覧ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
J・S・バッハ
平均律クラヴィーア曲集第1巻第一番プレリュード
無伴奏チェロ組曲第1番ト長調
無伴奏ヴァイオリンソナタ第2番イ長調
無伴奏ヴァイオリンパルティータ第2番ニ短調よりシャコンヌ
加藤氏は、身体全体をしなやかに使って弾く。その姿から、バッハの音楽を真正面から、全身で受け止めようとしていることをひしひしと感じた。打楽器は奏者の身体の動きがそのまま音になる部分が大きい。がっつりと音楽に取り組む身振りがダイレクトに音として立ちあらわれる。
実は、加藤氏のバッハ作品のCDはリリースされてまもなく聴いていたのだけれど、その演奏スタイルに違和感を覚えていた。なぜこれほどに大きな身振りが必要なのか。今回、実演に接してようやく身振りの意味合いがわかった。すると、音楽の中へどんどん入っていくことができた。
一曲目の「プレリュード」も、無伴奏チェロ組曲も、どことなく土の香りがした。マリンバの起源はアフリカにあるという話に、響きの面からリアリティを感じた。ただ、「土」といっても、土俗的というような意味合いではない。掘り起こしたばかりの土の、しっとりと水分を含んだ香り。ちぎれた草の根の匂いも混じった香り。豊かな滋味を含んだ土の、複雑な香りである。加藤氏の演奏は大地に足をつき、そこから得た力でバッハの世界とがっつり組み合っているように感じる。
ヴァイオリン・ソナタの第1楽章や第4楽章では硬めのマレットを使い、無伴奏チェロ組曲とは全く異なる響きを聴かせる。他方、3楽章のアンダンテでは再び柔らかめのマレットを使い、今夜初めて本格的なトレモロを使っていた。響きが楽想と見事に調和している。
今夜の演奏では、概してトレモロの使用を抑制し、自然減衰する単音の響きを重視していると思った。この楽器自体のシンプルな音で勝負しようという姿勢が潔い。
最後の「シャコンヌ」も実に気迫の籠った演奏だった。演奏後の挨拶で、「シャコンヌ」は初披露だったと語られた。コロナ禍による外出制限の中、演奏の機会も失われ、音楽に向かう気持ちを失っていた折、たまたま耳にしたブゾーニによる編曲にインスパイアされたものだという。
この作品は従来さまざまなトランスクリプションがあるのだけれど、改めてなんと複雑な音楽かと感嘆した。実に魅力的なモチーフを得たバッハは、書き進めるうちに筆が止まらなくなったのではなかろつかと、演奏を聴きつつ想像した。作曲家は自身の持つリソースを限界まで使い倒すことによって、ひとつの宇宙を構築してしまった。バッハは、実は編成を固定するつもりはなかったー途中からそのつもりがなくなってしまったーのかもしれない。もしかするとヴァイオリンのために書いたのは、楽想をリアライズするのに最も効率的だったというプラクティカルな理由だったのではなどとも妄想した。
アンコールにヴァイオリン・ソナタ第3番のラルゴ。
加藤氏の奏でるバッハ作品は一音一音に深く着実な思索が感じられる。単に楽器を置き換えたなどというものとは全く異なる音楽である。しかし、過度に学究的になることがない。無伴奏チェロ組曲のメヌエットやジーグなどではリズムが息づいていて舞曲集であることを思い出させてくれる。味わいのある響きにいつまでも包まれていたいと思った。
今後も引き続き取り組むというバッハが楽しみである。できる限り追いかけたい。
(2024年3月5日 鶴見区民文化センター サルビアホール 音楽ホール)
加藤訓子ソロリサイタルシリーズ in サルビアホール vol.2 レポート Read More »